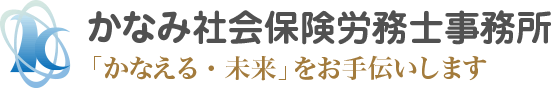障害年金の障害認定日の原則と特例 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金の請求を代行
障害年金を請求する際、「初診日」と同じように重要になるのが「障害認定日」です。
障害認定日は、障害の程度の認定を行うべき日をいい、原則的なルールと、病気やケガの種類によって認定日が早まる「特例」があります。
ここでは、障害認定日の原則と、知っておくべき特例について詳しく解説します。
1. 障害認定日とは
「障害認定日」とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日、または1年6か月以内にその傷病が治った場合においてはその治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。
障害認定日に、国民年金法施行令別表・厚生年金保険法施行令別表第1および第2に定める障害の程度に該当する状態であれば、翌月から障害年金が支給されることになります。
2. 障害認定日の原則
障害認定日の原則は、初診日から起算して1年6か月を経過した日です。
【原則】
初診日 + 1年6か月 = 障害認定日
初診日から1年6か月経った時点で、障害の状態にあるかどうかを判断し、診断書を作成してもらうことになります。
3. 障害認定日の例外
障害認定日の原則は「初診日から起算して1年6か月を経過した日」ですが、20歳前傷病の場合は例外です。
20歳前傷病とは、20歳に達する前に初診日がある方が対象となる障害基礎年金をいい、障害認定日は以下のいずれか「遅い日」になります。
- 20歳の誕生日の前日(満20歳に達した日)
- 初診日から1年6か月経過した日
例えば、初診日が18歳10か月の時であれば、1年6か月経過した日は20歳4か月になります。
20歳の誕生日の前日よりも遅くなるため、障害認定日は20歳4か月になります。
知的障害の方の場合は、出生日が初診日となるため、障害認定日は20歳の誕生日の前日となります。
4. 障害認定日の特例
障害認定日は、初診日から起算して1年6か月を経過した日が原則ですが、1年6か月以内に傷病が治った場合(症状固定)は、その日が障害認定日とされます。
障害年金における「治った(症状固定)」とは、身体的欠損や機能障害が残り、医学的にこれ以上の治療効果が期待できない状態に至ったことを指します。
特例として扱われる例
| 傷病・治療の内容 | 障害認定日 |
|---|---|
| 人工透析療法を行っている場合 | 透析を開始した日から起算して3か月を経過した日 |
| 人工弁・心臓ペースメーカー・ICD等を装着した場合 | これらを装着した日(手術日) |
| 人工関節・人工骨頭を挿入した場合 | 挿入置換した日(手術日) |
| 人工肛門の造設・尿路変更術 | 造設または手術日から6か月を経過した日 |
| 新膀胱を造設した場合 | 造設した日 |
| 手足の切断・離断の場合 | 切断または離断した日(原則として手術日) |
| 脳血管疾患による肢体障害 | 初診日から6か月以上経過し、それ以上の機能回復が望めないと医学的に認められる日 |
5. 最後に
本ページの内容は、障害認定日の基本ルールについてまとめたものです。
障害年金の制度や運用は変更されることがあるため、実際に請求される際は、以下の機関や専門家へ相談することをおすすめします。
- 最寄りの年金事務所(最新の認定基準の確認)
- 日本年金機構の公式ホームページ
- 障害年金に詳しい社会保険労務士
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2025年4月1日障害年金額令和7年度(2025年度)障害年金の年金額
- 2025年2月1日障害年金の請求手続き知的障害の障害年金と就労の関係
- 2025年1月20日障害年金制度障害年金の初診日とは
- 2024年4月1日障害年金額令和6年度(2024年度)障害年金の年金額
前後記事&カテゴリ記事一覧
- 前の記事:令和5年度(2023年度)障害年金の年金額
- 次の記事:令和6年度(2024年度)障害年金の年金額
- カテゴリ: