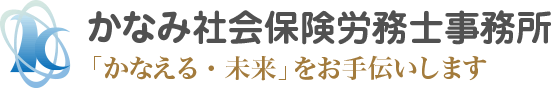障害年金の請求手続きの進め方 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金の請求を代行
障害年金の請求手続きには、障害の原因となった傷病の初診日を証明する「受診状況等証明書」の取得や「病歴・就労状況等申立書」の作成、診断書の取得など、様々なステップが必要で、事前準備をしっかり行い、一つ一つの手続きを確実に進めていくことが重要です。ここでは、障害年金の請求手続きの進め方や注意点などについて解説いたします。
初診日の確認
「障害認定基準」において「初診日」とは、障害の原因となった傷病について、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことをいい、障害年金の請求において非常に重要なポイントになります。まずは、病気やけがによって初めて受診した時期や医療機関を思い出します。正確な日付は、「受診状況等証明書」により確定されますが、この時点では、「〇年頃」や「〇年〇月頃」ぐらいは特定しておきます。
初診日の考え方の例
| 傷病名 | 経緯 | 初診日 |
|---|---|---|
| うつ病 | 偏頭痛や耳鳴り、嘔気などにより神経内科を受診。その後、精神疾患の可能性があると言われ、精神科の受診を勧められた。 | 精神科ではなく、神経内科を受診した日 |
| 多系統萎縮症 | 目眩の症状があったため耳鼻科を受診。その後、神経内科で多系統萎縮症と診断された。 | 多系統萎縮症の診断を受けた日ではなく、目眩症状で耳鼻科を受診した日 |
| 脳梗塞 | 高血圧の治療中に脳梗塞を発症して救急搬送された。 | 脳梗塞により救急搬送された日(高血圧と脳梗塞は相当因果関係なし) |
| 糖尿病性腎症 | 糖尿病の治療中に腎不全(糖尿病性腎症)となった。 |
糖尿病で最初に受診した日(糖尿病と糖尿病性腎症は相当因果関係があり)
|
| 知的障害 | 成人以降に知的障害と分かった。 | 「先天性の知的障害」であれば、出生日 |
保険料の納付要件を確認する
 障害年金を受給するには、保険料の納付要件を満たしていることが必要であります。
障害年金を受給するには、保険料の納付要件を満たしていることが必要であります。
保険料納付要件には、以下の2つの基準があります。
- 初診日の前々月におけるすべての被保険者期間のうち、2/3以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であること
- 初診日の前々月における直近1年間に未納期間がないこと
なお、20歳前に「初診日」がある人については、保険料納付要件は問われません。
保険料の納付要件は、年金事務所や街角の年金相談センター、市町村役場の国民年金課で確認します。
「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」での確認では不十分です。保険料納付要件を確認する際は、初診日より前に納付(申請免除)申請を行っている必要があり、「ねんきん定期便等」では納付日や免除の申請日までは確認できないからです。
保険料の納付要件を満たさない可能性がある場合
年金事務所などで確認した結果、「保険料納付要件を満たさない」と言われた場合でも、初診日の考え方によっては保険料納付要件を満たす場合もあります。
- 初診日の考え方が間違っている場合
障害年金の初診日は、障害の原因となった傷病名が確定した日ではありません。例えば、障害名がうつ病であっても、初診日が偏頭痛や耳鳴り、嘔気などの症状で受診した神経内科である場合や、ストレスによる胃痛で受診した内科が初診日となることもあります。このような場合、初診日が精神科ではないため、保険料の納付要件を再確認する必要があります。 - 20歳より前に初診日がある場合
障害の原因となった傷病により、20歳より前に初診日がある場合は、保険料納付要件を問われません。 - 先天性の疾患である場合
例えば、先天性の知的障害の場合、出生日が「初診日」となります。発達障害でも、知的障害を伴う場合は出生日が「初診日」となるため、保険料納付要件を問われません。 - 社会的治癒を主張できる場合
社会的治癒とは、「症状が安定して特段の治療の必要がなくなり、社会生活が長期間可能である場合」をいいます。
社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の社会活動や日常生活が可能な場合は、「社会的治癒」とされます。
この場合、医学的な治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱われるため、受診を再開した日が「初診日」と認められることがあります。
受診状況等証明書を取得する
「初診日」を証明するための書類が「受診状況等証明書」で、初診の医療機関に作成してもらいます。
初診の医療機関の診療録が廃棄されている場合は、「受診状況等証明書」を作成できないため、2番目に受診した医療機関で作成してもらいます。そして、「受診状況等証明書」が作成できなかった医療機関に関しては、「受診状況等証明書が添付できない申立書」を作成し、初診日を補足できるような証明資料を用意します。
なお、初診日から障害年金の請求時まで同じ医療機関に通院している場合、初診日は「診断書」で確認できるため、「受診状況等証明書」は必要ありません。また、知的障害や知的障害を伴う発達障害など、出生日が初診日とされる場合も「受診状況等証明書」は不要です。
初診日は必ず特定する必要があります
初診日が認定されるための証明資料は、初診日に係る診療に直接関与した医師(医療機関)が作成したもの、または、この診療について当時作成された診療録等の記載に基づき医師(医療機関)が作成したもの、あるいは、これらに準ずるような証明力の高い資料でなければならないとされています。
「受診状況等証明書が添付できない申立書」は、初診の医療機関で初診日が確認できない場合に、その他の参考資料を基にで初診日の認定を求めるための書類です。自己申告だけでは初診日が認定されることはありません。重要なことは、「初診日」が曖昧なまま障害年金の手続きを進めないことです。
【証明資料の例】
- 障害者手帳の申請時の診断書
- 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 母子健康手帳
- 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
- お薬手帳・糖尿病手帳・領収証・診察券など(診察日や診療科が記載されているもの)
- 小中学校の健康診断の記録や成績通知表
- 盲学校・ろう学校の在学証明・卒業証書
- 第三者証明(初診の頃の様子を知っている第三者に記載してもらう書類)
病歴・就労状況等申立書を作成する
「病歴・就労状況等申立書」とは、障害年金を請求する際に必要な書類であり、病歴や日常生活状況、就労状況などを具体的に記載するものです。この申立書は、医師が作成した「診断書」を補完する役割を果たします。
申立書には、発病の時期や発病から初診までの状況、治療の経過、病状、日常生活状況、就労状況などを、時系列に空白期間がないように記入します。
「病歴・就労状況等申立書」は、診断書だけでは伝えきれない情報や、障害によって困っていることを審査する側に伝えるための重要な書類です。読みやすさを考慮しながら、必要な情報を過不足なく記入することが求められます。
診断書を取得する

医師に「診断書」を作成してもらいます。
障害年金で使用する診断書は全部で8種類あり、ご自分の障害状態を適切に伝えることができるものを使用します。
| 診断書の種類 | 対応する傷病名 |
|---|---|
| 眼の障害用 | 緑内障、網膜色素変性症など |
| 聴覚・鼻腔機能・平衡機能・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用 | メニエール病、感音性難聴、喉頭癌、舌癌など |
| 肢体の障害用 | 脳血管疾患による肢体障害、関節リウマチ、筋ジストロフィー、パーキンソン病、変形性股関節症など |
| 精神の障害用 | うつ病、双極性障害、統合失調症、広範性発達障害、知的障害など |
| 呼吸器疾患の障害用 | 肺結核、じん肺、気管支喘息、慢性気管支炎、肺気腫など |
| 循環器疾患の障害用 | ペースメーカー、ICD、難治性不整脈、大動脈疾患など |
| 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用 | 慢性腎不全、肝硬変、1型糖尿病など |
| 血液・造血器・その他の障害用 | 悪性貧血、悪性新生物、その他上記に分類できない傷病など |
障害年金の請求方法と診断書の枚数
障害年金の請求方法には「障害認定日請求」と「事後重症請求」の2種類があり、それぞれ必要な診断書の枚数が異なります。
| 請求の種類 | 概要 | 必要な診断書 | ぞの他 |
|---|---|---|---|
| 障害認定日請求 | 初診日から1年6ヶ月経過した日を「障害認定日」とし、その時点で障害状態に該当する場合 | 障害認定日以降3ヶ月以内の現症の診断書が1枚必要 | 障害認定日から1年以上経過している場合は、請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書も必要になります。 |
| 事後重症請求 | 障害認定日には障害状態になかったが、その後状態が悪化した場合 | 請求日以前3ヶ月以内の現症の診断書が1枚必要 |
その他必要書類を準備する
「受診状況等証明書」「診断書」「病歴・就労状況等申立書」などの書類の他にも様々な書類を用意する必要があります。
必要な書類は、年金事務所または市役所でご確認ください。代表的なものは、「年金請求書」や「年金生活者支援給付金請求書」、年金振込口座が確認できる分かるものです。
障害年金を請求する
提出書類は、請求後に内容を確認する必要が生じた場合に備えて、必ずコピーを取っておきましょう。
障害年金の請求書類の提出先は、「初診日」や加入していた年金制度によって変わります。
- 障害基礎年金
住所地を管轄する市区町村役場 - 障害基礎年金(初診日に第3号被保険者の場合)
年金事務所または街角の年金相談センター - 障害厚生年金
年金事務所または街角の年金相談センター - 障害厚生年金(初診日に旧共済組合の被保険者の場合)
初診日に加入していた共済組合
最後に
ここでは、障害年金の請求手続きの進め方について解説しました。
障害年金を請求する際は、必要な知識を把握した上で、年金事務所に足を運び、正しい手順で手続きを進める必要があります。
障害年金の手続きは複雑で、一般の方には分かりにくい点も多いため、不安や疑問がある場合は、社会保険労務士に相談することをおすすめします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2025年4月1日障害年金額令和7年度(2025年度)障害年金の年金額
- 2025年2月1日障害年金の請求手続き知的障害の障害年金と就労の関係
- 2025年1月20日障害年金制度障害年金の初診日とは
- 2024年4月1日障害年金額令和6年度(2024年度)障害年金の年金額
前後記事&カテゴリ記事一覧
- 前の記事:障害年金を受給するための要件
- 次の記事:障害手当金
- カテゴリ: