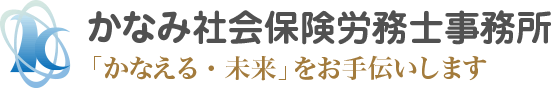喉頭全摘出で障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所/障害年金申請(請求)を代行
喉頭全摘出により、日常生活や労働に著しい支障が出ている場合、障害年金の対象となる可能性があります。障害年金を申請(請求)するためには、初診日や障害の状態などの情報が求められ、正確に手続きを行うことが大切です。ここでは、喉頭全摘出によって障害年金を申請(請求)する方法やポイントについて解説いたします。
喉頭全摘出の障害認定基準
喉頭全摘出で言語機能の障害となった場合の障害年金認定基準は次のようになっており、それぞれの等級によって支給額が決まります。※3級は障害厚生年金のみ
支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
言語機能の障害認定基準
喉頭全摘出による「言語機能の障害認定基準」は次のとおりです。
| 等級 | 障害の状態 |
|---|---|
| 2級 | 発声に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないものをいう。 |
| 3級 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいう。 |
| 障害手当金 | 話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つものをいう。 |
- 音声又は言語機能の障害とは、発音に関わる機能又は音声言語の理解と表出に関わる機能の障害をいいます。
- 構音障害、音声障害又は聴覚障害による障害については、発声不能な語音を評価の参考にされます。発声不能な語音は、次の4種について確認するほか、語音発語明瞭度検査等が行われた場合はその結果を確認されます。
・口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音等)
・歯音、歯唇音(さ行、た行、ら行等)
・歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
・軟口蓋音(か行音、が行音等)
障害年金の申請(請求)の進め方
喉頭全摘出で障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
-
「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能)の障害用」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
喉頭全摘出で障害年金を申請(請求)するポイント

ポイント1 障害年金の初診日は
障害年金の「初診日」とは、障害の原因となった傷病により、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日とされます。
声のかすれや喉の違和感などで病院を受診した日が、障害年金を申請(請求)する際の初診日になります。
ポイント2 障害年金はいつから申請(請求)できる?
通常、障害年金は初診日から1年6か月経過した時点から請求することができますが、喉頭全摘出手術を施している場合には、「喉頭全摘出手術日」から障害年金を申請(請求)することができます。(ただし、1年6か月経過以降に喉頭全摘出手術を施している場合は、障害認定日は原則通り1年6か月時点となります)
・初診日から1年6か月経過前に喉頭全摘出手術を施した
すぐに障害年金の申請(請求)ができます。請求せずに相当期間が経っていても障害認定日時点の診断書があればその時に遡っての請求も可能になります。
・初診日から1年6か月経過後に喉頭全摘出手術を施した
原則通り、初診日から1年6か月経過した日が障害認定日となります。1年6か月時点で著しく日常生活に支障がでていない時には障害等級には該当せず、請求したときから障害年金を受給できることになります。
喉頭全摘出手術を施しても障害年金を申請(請求)していない場合は、過去に遡っても受給できませんので、すぐに請求する必要があります。1か月請求が遅れれば1か月分の年金が受け取れないことになります。
喉頭全摘出で障害年金の申請(請求)をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2025年1月8日内蔵疾患慢性腎炎(ネフローゼ症候群を含む)で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2024年12月21日肢体の障害変形性膝関節症で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2023年4月15日肢体の障害遷延性意識障害(植物状態)で障害年金を申請(請求)する方法を解説
前後記事&カテゴリ記事一覧
- 前の記事:感音性難聴で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 次の記事:肝硬変で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- カテゴリ:眼・耳・鼻・口の障害