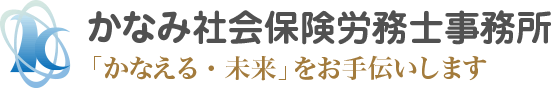てんかんで障害年金を申請(請求)する方法を解説 | かなみ社会保険労務士事務所
てんかん発作で日常生活に著しい支障が出ている場合には障害年金の対象になります。
ここでは、てんかんになった場合の障害年金の基準や申請(請求)手続きのポイントを解説します。
てんかんの障害年金認定基準
障害年金におけるてんかん発作の分類
てんかんの障害認定基準は、発作症状のタイプとして4つのタイプに分類されています。

| A | 意識障害を呈し、状況にそぐわない行為を示す発作 |
|---|---|
| B | 意識障害の有無を問わず、転倒する発作 |
| C | 意識を失い、行為が途絶するが、倒れない発作 |
| D | 意識障害はないが、随意運動が失われる発作 |
てんかんの発作症状のタイプによる障害年金の等級目安
上記4タイプの発作症状と発生頻度により各等級の目安が定めらています。※3級は障害厚生年金のみ 支給される障害年金額は等級別の障害年金の年金額をご参照ください。
| 等級 | 状態 |
|---|---|
| 1級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが月に1回以上あり、かつ、常時の介護が必要なもの |
| 2級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回以上、もしくは、C又はDが月に1回以上あり、かつ、日常生活が著しい制限を受けるもの |
| 3級 | 十分な治療にかかわらず、てんかん性発作のA又はBが年に2回未満、もしくは、C又はDが月に1回未満あり、かつ、労働が制限を受けるもの |
その他 障害認定基準で定められている事項
- てんかんは、発作と精神神経症状及び認知障害が相まって出現することがあります。この場合、精神神経症状や認知障害については、「症状性を含む器質性精神障害」に準じて認定されます。
- てんかん発作が出現し、発作間欠期に精神神経症状や認知障害を有する場合には、治療及び病状の経過、日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
- てんかんとその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行われず、諸症状を総合的に判断して認定されます。
障害年金の申請(請求)の進め方
てんかんで障害年金を申請(請求)する場合、手続きの進め方は次のようになります。
- 「初診日」を調べる。
- 「受診状況等証明書」取得する。
- 「病歴・就労状況等申立書」作成する。
- 「診断書(精神の障害用)」の作成を病院に依頼する。
具体的な手順はこちらのページで解説していますので、ご確認ください。
てんかんで障害年金を申請(請求)する際のポイント
ポイント1 発作症状と頻度に加えて社会的活動能力の損減が考慮されます
てんかん発作での障害年金の審査では、発作症状のタイプ以外にも、日常生活動作がどの程度損なわれ、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかという、社会的活動能力の損減を重視した観点から認定されます。
ポイント2 病歴・就労状況等申立書の記載内容は重要です

てんかん発作で障害年金を申請(請求)する場合、「病歴・就労状況等申立書」も重要です。
発作頻度に加えて、発作間欠期で日常生活動作がどの程度損なわれており、そのためにどのような社会的不利益を被っているのかを審査側に伝えましょう。
てんかんで障害年金をサポートした事例集
弊所が担当させていただいた案件を一部ご紹介いたします。
てんかん発作で約40年間 障害年金を未請求 初診日証明が非常に困難だった事例
「17歳時」に初めて意識を失う発作があり、その後は1か月に1度の頻度で全身のけいれん発作や意識を失う発作が続くようになりました。最初は20歳前傷病と考えられていましたが、年金記録に厚生年金の加入期間の漏れが見つかり、初診時に厚生年金の被保険者であることが明らかになりました。
このため、20歳前傷病から障害厚生年金での申請(請求)に変更し、初診日を証明する難しさが生じました。診療録の開示請求を行いましたが、「17歳」が初診だということ以外は分からなかったため、平成28年に初診日証明に関する取扱いが変更された情報を利用することに決めました。
新しい取扱いに基づき、「17歳時」のどの期間も厚生年金に加入しており、保険料納付要件(旧法・新法)を満たしていると主張し、初診(発病)の「年」だけを確定して請求を行いました。本人申請(請求)では難しいと思われる事例でした。(障害厚生年金2級)
ご不安な方は障害年金の専門家への相談をしましょう
実際に障害年金を申請(請求)する際には、障害年金に関する知識を抑えた上で、年金事務所へ足を運び煩雑な処理を正しい手順で進めていく必要があります。
障害年金は複雑で一般の方には難しい点も多々あります。不安や分からないことがある場合は、障害年金を扱っている専門家(社会保険労務士など)に相談しましょう。
最終更新日:
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2023年12月7日眼・耳・鼻・口の障害糖尿病性網膜症で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2023年4月15日肢体の障害遷延性意識障害(植物状態)で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2022年12月21日肢体の障害関節リウマチで障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 2022年5月31日眼・耳・鼻・口の障害緑内障で障害年金を申請(請求)する方法を解説
前後記事&カテゴリ記事一覧
- 前の記事:統合失調症で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- 次の記事:広範性発達障害(ADHD・ASD)で障害年金を申請(請求)する方法を解説
- カテゴリ:精神の障害