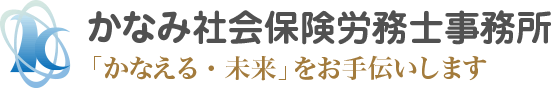50代男性 平山病・頚椎ヘルニアの後遺症で障害基礎年金1級を受給 | かなみ社会保険労務士事務所
| 大阪府大阪市
相談者の状況
平山病と診断されるまで
高校2年生の時に右手の人差し指が曲がらなくなり、握力が低下しているように感じました。当時はバンド活動(ギター担当)をしていましたが、指に力が入らないようになり、学園祭で演奏することができなかったようです。その後もうまく指が曲がらない状態が続き、全身にビリビリとした痺れを感じることもありました。
この頃にA県立病院を受診し、レントゲン検査などをしましたが異常はなく、医師から「ギターの練習で指を使い過ぎたからではないか」と言われていました。
高校3年生になってもギターを弾くことができなかったためにドラムを担当するようになりました。ドラムのスティックを右手に固定して演奏したようです。
高校を卒業後はバンド活動はやめていたにも関わらず症状は一向によくなりません。右手に加えて左手も筋力が低下しているように感じるようになりました。
20歳の頃にB病院を受診。約1か月近くの検査入院によって「平山病」と診断されました。21歳時に身体障害者手帳3級が交付されています。
未受診期間が続く
医師から「治療方法はなく、症状はある程度進行すれば収まる」と言われていため、病院を受診することがなくなりました。
両手の指先だけがどんどん痩せていき、手指が曲げにくい状態が続きました。
33歳の頃になると頸部から左肩にかけての痛みが出現し、左手の筋力が特に低下しているように感じるようになり、手指で物が持てなくなるほど症状が悪化しています。
頚椎椎間板ヘルニアで手術を行う
33歳の頃にC総合医療センターを受診。MRI検査で頚椎椎間板ヘルニアであると診断され、前方徐圧固定術(プレート使用)手術を行いました。術後の経過確認のために2年間は定期的に通院していましたが、その後は病院を受診することはなくなりました。
両手指の症状が悪化 歩行にも支障がでる
33歳の頃から両手の指が曲げられない状態は続き、物は両手で挟み込むようにして持つようになりました。両手の筋力が低下し、手指全体が細くなります。
40歳の頃には歩行の際に足がうまく出せないようになります。
頚髄萎縮 平山病 ・頚椎ヘルニアの後遺症と診断される
55歳の時にD総合病院を受診。症状が進行しているのは、平山病、頚椎ヘルニアの後遺症であると言われました。身体障害者手帳は、両全手指機能全廃で2級として更新されました。
平山病・頚椎ヘルニアの後遺症の病歴の整理
| 年齢 | 受診した医療機関 | 疾病名 |
|---|---|---|
| 17歳(高校2年生) | A県立病院 | |
| 20歳〜21歳 | B病院 | 平山病
身体障害者手帳3級が交付 |
| 21歳〜33歳 | 未受診期間 | |
| 33歳 | C総合医療センター | 頚椎椎間板ヘルニア |
| 34歳〜55歳 | 未受診期間 | |
| 55歳 | D総合病院 | 平山病・頚椎ヘルニア後遺症
身体障害者手帳2級(両全手指機能全廃) |
受任から申請(請求)までに行ったこと
平山病の初診日は約40年前 受診状況等証明書は取得できず
障害年金の制度では「初診日」を基準にして、請求する制度(国民年金・厚生年金)が確定し、初診日の前日までの保険料納付状況を確認されるため、「初診日」は非常に重要になります。
20歳前に初診日がある障害基礎年金の場合、保険料納付要件は必要ないものの、所得制限や国内居住制限などがあるため、初診日が20歳前か20歳後のどちらになっているか特定する必要があります。
平山病の初診日は高校2年生の17歳の頃、確定診断を受けたのは20歳の時です。
初診日を特定する書類が「受診状況等証明書」であり、初診の医療機関に作成を依頼することになるのですが、請求人の初診日は約40年近く前のことであり、A県立病院の診療録は廃棄されていました。
次にB病院の診療録を確認しましたが、A県立病院と同じように診療録は廃棄されています。平山病の経過観察は21歳で終了しており、障害年金の申請(請求)時まで未受診期間が続いたことから、平山病の「受診状況等証明書」は取得することはできませんでした。
第三者証明で障害年金の申請(請求)を考える
平山病の受診状況等証明書は取得できなかったため、バンド仲間に発病・初診時期を証明(第三者証明)してもらうことを考えました。バンド仲間のうち1人と連絡を取ることができ、高校時代の申請(請求)人のことを証言してもらうことになりました。
この方は、学園祭で演奏できなかったことや、高校3年生の時にドラムのステックをテープで手に巻き付けて演奏していたことが衝撃的だったことから、当時のことを鮮明に記憶に残っていました。
第三者証明は原則として複数人の証明が必要とされているのですが、この方の第三者証明のだけで初診日が認められる可能性があると考え、障害年金の申請(請求)を行うことにしました。
D総合病院で診断書を取得
55歳時に身体障害者手帳が2級(両全手指機能全廃)として更新されていたことから、身体障害者手帳の診断書を市役所から取得しました。身体障害者手帳の傷病名は「両上肢の弛緩性麻痺」で、原因となった疾病・外傷名は「平山病」となっていました。障害年金用の診断書も同様の傷病名であると考えます。ところが、障害年金用の診断書を取得したところ、傷病名は「頚髄萎縮:平山病、頚椎ヘルニアの後遺症」と記載されています。
頚椎ヘルニアの受診状況等証明書を取得 診療録の開示請求
「平山病」で障害年金の申請(請求)を考えていましたが、「頚椎ヘルニアの後遺症」が診断書の傷病名に記載されていたため、頚椎椎間板ヘルニアで入院したC総合医療センターで受診状況等証明書の作成依頼を行いました。受診状況等証明書の発病から初診までの経過欄には、「33歳時に両上肢の筋力低下が出現したため、当院を受診」との記載がありました。
C総合医療センターの診療録の開示請求を行う
受診状況等証明書の依頼と同時に、C総合医療センターの診療録の開示請求を行いました。診療録の開示請求の目的は「平山病」の情報が記載されていないか確認するためです。
数週間後に診療録を取得することができ、内容を確認すると「17ya 平山病発症 右上位優位の筋力低下」との記載がありました。17歳で平山病を発症したことが診療録によって確認することができたのです。
平山病・頚椎ヘルニアの後遺症の障害の程度

頸椎の障害のために左下肢が痙性歩行障害となっており、両手指は少し動く(曲げる)ことができるものの、書字の際は両手でペンを挟んで所持しなければならない状態で、実用的な動作はまったくできません。
上肢と下肢に障害があるのですが、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合は、障害の重い方で認定するようになっています。
申請(請求)人は上肢の障害の方が重く、「両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの」、これは障害基礎年金1級として認定されると考えました。
結果
障害基礎年金2級として決定されました。
障害等級を争って審査請求を行う。
上肢の障害で認定されるべきものが、肢体の障害で認定されたことから、不服申し立て(審査請求)を行うことになりました。
請求人の障害は上肢の障害で認定するように求めたものの、審査請求では棄却。棄却決定後すぐに再審査請求を行ないます。
約6ヶ月後、公開審理の案内が届き、公開審理に出席する準備をしていたところ、日本年金機構が処分を変更したという連絡が社会保険審査会から入りました。
最終結果
年金種類と等級;障害基礎年金1級
年金額:年額975,000円
その他
投稿者プロフィール

最新の投稿
- 2024年7月15日精神の障害20代女性 自閉症スペクトラム障害で障害基礎年金2級を受給
- 2024年7月15日精神の障害20代男性 アスペルガー症候群で障害基礎年金2級を受給
- 2024年5月3日精神の障害発達障害と統合失調症が併存している場合 統合失調症で障害厚生年金2級を受給
- 2024年4月21日精神の障害障害者雇用で社会保険に加入 3回目の申請(請求)で障害基礎年金2級が決定